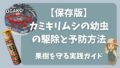はじめに
先日、庭で枝豆を収穫しました。塩ゆでして食べると、豆の味がぎゅっと詰まって香りも豊か。やっぱり採れたては格別です。
でも、収穫後には「葉や茎、根っこ」などのたくさんの残りもの(残渣=ざんさと呼びます)が出ますよね。普通ならゴミ袋行きですが、これを土に返して堆肥(たいひ)にすると、畑の土をもっと元気にできるんです。
今回は、初心者でもできる「枝豆の残渣を堆肥化する方法」として、カルスNC-Rと米ぬかを使ったやり方をご紹介します。
残渣(ざんさ)ってなに?

「残渣」とは、収穫後に残る植物の葉・茎・根などのこと。
これをそのまま捨てずに堆肥(たいひ)=微生物の力で分解された土の栄養材に変えると、畑がふかふかになり、次の野菜が元気に育ちます。
残渣を堆肥化するメリット
- 土がふかふかになる
→ 水や空気がよく通り、根がのびのび育つ。 - じんわり効く肥料効果
→ 化学肥料のように一気に効かず、長期間ゆっくり土を肥沃にする。 - ゴミを減らせる
→ 生ごみや野菜くずを土に返せるので、環境にもお財布にも優しい。 - 微生物やミミズが増える
→ 土の中の小さな生き物が活発になり、病気に強い土をつくる。 - 循環型の暮らしに
→ 「食べる → 残渣を堆肥にする → また育てる」という自然のサイクルを実現。
堆肥化で気をつけたいこと
- 高温発酵をさせる
60〜70℃くらいに上がると、病原菌を死滅させて安全に。 - 病気の植物は別処理
ウイルス性の病気が出た枝豆は、畑から離れた場所で処理。 - 放置しない
そのまま残しておくと害虫や菌が増えるので、早めに堆肥化を開始。 - 入れすぎに注意
残渣が多すぎると分解が遅れて、土の栄養バランスが崩れることも。 - 水分・温度管理を忘れずに
乾燥すると分解が止まるので、水を足しつつ、直射日光や雨を避ける。冬は保温も大事。
材料紹介:「カルスNC-R」と「米ぬか」

カルスNC-Rとは?
リサール酵産が開発した「土づくり資材」です。
- たくさんの微生物が入っていて、残渣の分解を助ける。
- 分解途中でも作物を植えられるので、畑の管理がスムーズ。
- 土の中の悪玉菌を抑え、土を健康にする働きがある。
米ぬかとは?
お米を精米したときに出る粉。
- 微生物の大好物なので、発酵が一気に進む。
- 安価で手に入りやすく、堆肥化にぴったり。
実際の手順:枝豆の残渣を堆肥化する方法
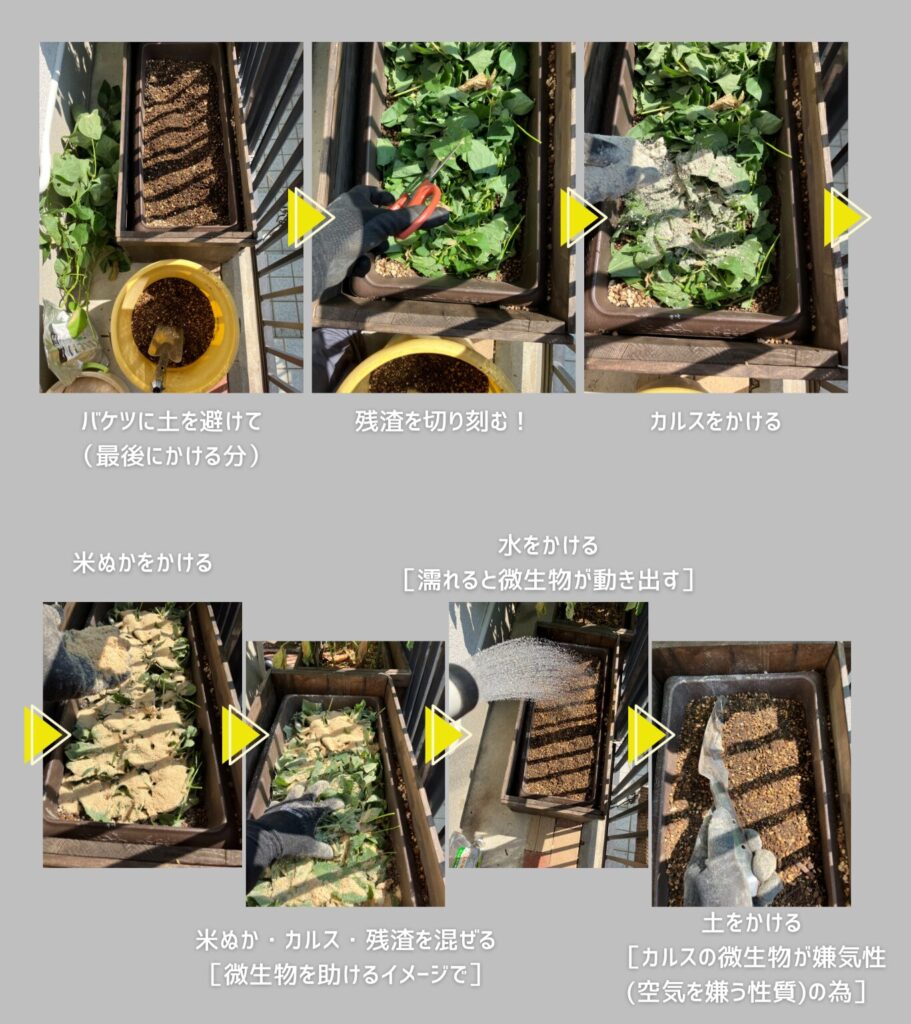
- 残渣を小さく切る
→ 細かいほど分解が早い。 - 混ぜる
→ 枝豆の残渣+カルスNC-R(残渣全体にうっすらかかるくらい)+米ぬか(カルスの5倍量)をよく混ぜる。
→ 層状に重ねてもOK。少量の土を混ぜると微生物が増えやすい。 - 水をかけて水分調整
→ 手で握ったときに軽くまとまるくらいがベスト。 - 寝かせる(発酵させる)
→ ビニールで覆って放置。地温15~35℃(深さ15~18cm)ならば、1〜3週間で土のような見た目に。(今回は土を被せただけで、ビニールは使いませんでした) - 完成チェック
→ ふかふかで、嫌な臭いがしなければ完成。畑に戻してOK!(今回は収穫後のプランターで土作りしています)
まとめ
- 枝豆を食べた後に出る葉や茎も、カルスNC-Rと米ぬかを使えば堆肥に変えられる。
- 微生物の力で安全に早く分解でき、土がふかふかに。
- ゴミを減らしながら、自然のサイクルを楽しめる。
「おいしい枝豆を食べて、残りを土に返して、また育てる」――そんな循環の暮らし、あなたも始めてみませんか?